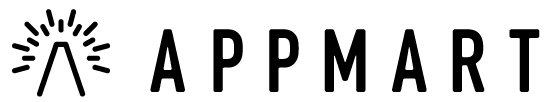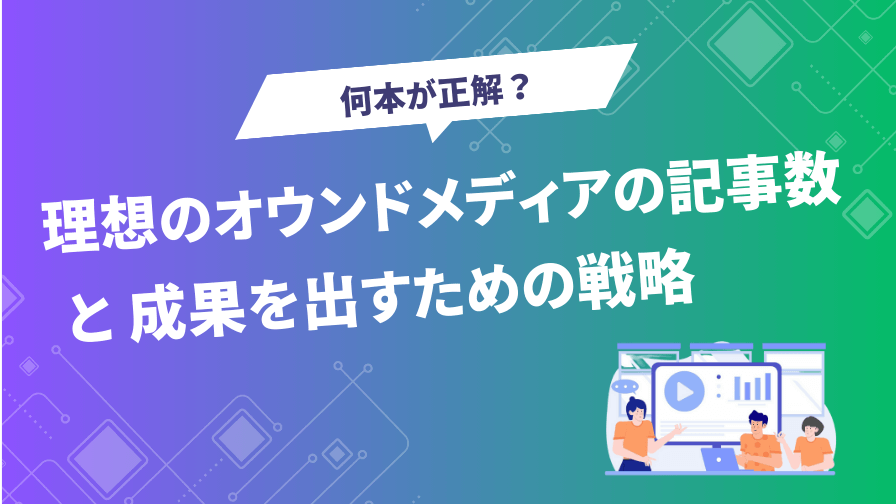<この記事でわかること>
- SEOで成果を出すために必要なオウンドメディアの記事数の目安と考え方が理解できる
- 検索意図に沿った構成で記事を体系的に設計する方法がわかる
- 記事数を効率的に増やすための体制構築と運用のポイントが学べる
オウンドメディアで集客や認知拡大を目指す企業にとって、「どれくらいの記事が必要か」という疑問は避けられません。記事数はSEOに直結し、流入やコンバージョンに大きく影響します。
しかし、やみくもにオウンドメディアの記事数を増やせば成果につながるわけではなく、「質と量のバランス」や「成長フェーズに応じたKPI設計」も欠かせない視点になります。たとえば、目指すセッション数に合わせて、どの程度の記事数が必要なのか、把握することが重要です。
そこで本記事では、SEOの専門知識と多数のオウンドメディア支援実績を持つ弊社Appmartが、成果に直結するオウンドメディアの記事数の目安と、戦略的な記事の増やし方を徹底解説します。ぜひ、貴社のオウンドメディア運用にお役立てください。
もくじ
オウンドメディアで成果を出すために必要な記事数の目安とは?

オウンドメディアで成果を出すための記事数の目安は「30〜50記事」が目安ですが、これは“最低ライン”に過ぎません。
最終的には成果(PV数・セッション数・コンバージョン)の逆算から、自社にとって最適な記事の数を戦略的に設計するのがポイントです。
なぜこの目安が出るのかというと、一定数の記事数がないと、サイト全体の検索上位表示や回遊、ドメイン評価が進まないためです。一方で、単に記事数だけを増やして「重複コンテンツ」や「記事の質の低下」が起きると、SEO効果が落ちるリスクもあります。
そのため、量(記事数)と質(専門性・独自性・構成・検索順位など)の両立が必要です。
具体的には、少なくとも30記事以上を公開することで、検索エンジンとユーザーの双方に信頼されやすいメディアとして認識される指標があります。
ただし、最適な記事数に絶対的な正解は存在しません。記事数は、業界やターゲット、競合状況、自社のKPIに応じて逆算設計するのが重要です。
以下は、オウンドメディアのジャンル・状況別に想定される記事数をまとめた内容です。
| 条件・状況 | 解説 |
|---|---|
| オウンドメディア運営の開始時 | 一般的に30〜50記事を用意して運営をスタートするケースが多い |
| 専門的な分野のオウンドメディアの場合 例:Webマーケティング情報サイト |
良質な内容なら、少ない記事数でも高いPV数を出し続けられる可能性あり |
| 新しい情報を扱うオウンドメディアの場合 例:面白ニュースや雑学のサイト |
新しい記事を継続してアップすることで、PV数を維持しやすい |
| 60記事以下の場合 | 記事数を増やすこと自体でSEOで上位化する可能性あり |
| 達成したい成果が決まっている場合 例:月20件の問い合わせを得たい |
CVRから必要な記事数を逆算する |
オウンドメディアは「記事数」に加えて「質(構成・専門性・独自性)」+「内部リンクによる関連性」を三位一体で設計するのが重要です。
オウンドメディアやコンテンツマーケティングでは記事数に加え、1記事あたりの文字数もSEO効果に影響します。ユーザーの検索意図を十分に満たせるよう「2,000~3,000文字以上」を目安に、質の高い情報を網羅的に提供するのが大切です。
このようにオウンドメディアを設計すると、検索エンジンもユーザーも信頼できるメディアと認識しやすくなり、成果(PV・セッション・CV)に結びつく可能性が高まります。
SEOで効果が出るまでの平均記事数
SEO効果を実感するためには、一定ラインの記事数を質とともに戦略的に増やす必要があります。
理由として、記事数単独で検索上位になるわけではなく、ドメインの信頼性・記事コンテンツの品質・専門性・網羅性などと組み合わさって成果が得られるためです。
つまり、SEOで効果を出す上で重要なのは記事数そのものではなく、目標達成のために逆算された戦略的な記事数設定と、その継続可能な実行体制の構築です。記事数を増やす際には「内部リンク」「網羅性」「質の維持」も合わせて設計した上で、量だけでなく成果につながるコンテンツ量を形にするアプローチがポイントとなります。
オウンドメディアの成長ステップ別・記事数の目安
オウンドメディア運営では、以下のように各成長フェーズに応じた記事数の確保と更新頻度が重要です。
| 成長フェーズ | 時期の目安 | 推奨記事数 | 更新頻度の目安 | 重視すべき要素 |
|---|---|---|---|---|
| 立ち上げ期 | 0〜3〜6か月 | 30〜50記事 | 週2〜3記事程度 | コンテンツの厚み、初期流入、内部リンク設計 |
| 成長期 | 6か月〜1年 | 50〜200記事前後 | 週1〜2記事程度 | SEO対策、検索上位表示、回遊性 |
| 安定期 | 1年以降 | 200記事以上 | 月2〜4記事程度 | リライト、CVR改善、質の維持 |
「ただ記事数を追う」のではなく、成長フェーズに応じて読者とSEO双方に強いオウンドメディアを目指しましょう。
オウンドメディアの記事数を増やす3つのメリット
記事数を増やすことは、オウンドメディアにおける集客・信頼性・流入経路の強化に直結する強力な戦略です。
- 検索流入キーワードの幅が広がる
- 内部リンク設計によりサイト内の回遊性が高まる
- ドメイン評価(ドメインパワー)が上がりやすくなる
オウンドメディアの記事数を増やすことによる上記メリットについて具体的に解説します。
検索流入キーワードの幅が広がる
記事数を増やすことで、対応可能な検索キーワードが増え、結果的に検索の流入経路が多様化して集客力が拡大します。検索流入の入口が増えれば、セッション数やアクセス数の向上にもつながる点がメリットです。
たとえば、ファッション系オウンドメディアで「秋コーデ特集」「ブランド別コーデ事例」「トレンドアイテムの着こなし方」といった異なる切り口で記事を作成します。
すると、「秋 コーデ 20代」「ユニクロ コーディネート」「ワイドパンツ 着回し」など異なる検索クエリからもユーザーを集客できます。
さらに「黒スキニー メンズ 春」「白Tシャツ レディース コーデ」のようなロングテールキーワードも組み込めば、小さなアクセスを積み重ねて全体の流入を底上げすることが可能です。
つまり、記事数を増やすことは単なる量の拡充ではなく、ユーザーの検索ニーズに多角的に応える窓口作りにほかなりません。これによって、流入の質と量の両方の底上げを実現します。
内部リンク設計によりサイト内の回遊性が高まる
記事数が増えれば、関連性の高い内部リンクを設計しやすくなり、サイト内での回遊性が向上します。
内部リンクは、ユーザーが別の記事へと自然に移動する導線を作り、ページ滞在時間を延ばせるのが特徴です。また、内部リンク設計がしっかりしているサイトはクローラーも巡回しやすくなり、インデックス率やSEO評価が高まるメリットもあります。
たとえば、キャンプ用品のオウンドメディアで「テントの紹介記事」から「ランタンの選び方記事」にリンクを設定すると、ユーザーは関連コンテンツを連続して読む可能性が高まります。これにより離脱率の低下や、回遊数増加につながる点がメリットです。
このように、記事数の増加は、読者を次の記事へ導く設計力を強化します。
ドメインパワー(ドメイン評価)が上がりやすくなる
多くの記事を蓄積するとインデックス数が増加し、内部リンク網も豊かになるため、ドメインパワーが向上しやすくなります。
検索エンジンは、ユーザーが欲しい情報を一つの記事で完結できる網羅性と、理解しやすい見出し・階層構造で整理された記事を高く評価します。そして、インデックス登録のページ数が多く、内部リンクが充実しているサイトを信頼性の高いリソースと判断し、総合的なSEO評価を高めるのが特徴です。
要するに、記事数を増やすことは、ドメイン評価を育てる土台作りと言えます。
オウンドメディアの記事数を増やす2つのデメリット
オウンドメディアの記事数を増やすことには、以下のように知っておくべき注意点もあります。
- 運用・管理コストが増加する
- コンテンツの質が低下するリスクがある
オウンドメディアの記事数増加にはどのようなデメリットがあるのか、対策とともに解説します。
運用・管理コストが増加する
記事数を増やすと、制作だけでなく、管理体制や分析体制を含めた運用・管理コストが増加します。
多くの記事を安定的に公開・更新し続けるには、ライターや編集者の人的リソースや、記事構成・キーワード戦略・SEO分析を担う運用体制が必須です。さらに、外注する場合はその分の外注費も発生します。
記事数を増やす場合は、記事の質と継続性に投資する構えでないと、成果につながりにくい運用になりがちです。
記事数を増やす際は、数だけを増やすのではなく、「どの部分を内製化し、どこを外注すべきか」を見極めた上で、予算と体制に応じた運用設計を行いましょう。
コンテンツの質が低下するリスクがある
記事数の増加ばかりを重視すると、コンテンツの構成や深掘りが薄くなり、結果として質が低下するリスクがあります。
量産型の記事を優先すると、記事構成や読みやすさ、独自性、専門性が犠牲になりがちです。すると、ユーザーの信頼を獲得しにくくなりかねません。検索上位に表示されたとしても、記事の質が低いとクリック率や滞在時間が低下し、SEO評価にもマイナスの影響が出る可能性があります。
記事の「量」と「質」の両輪で戦略的に積み上げる設計こそが、オウンドメディア成功の本質と言えるでしょう。
オウンドメディアは記事数より「質と量のバランス」が重要な理由
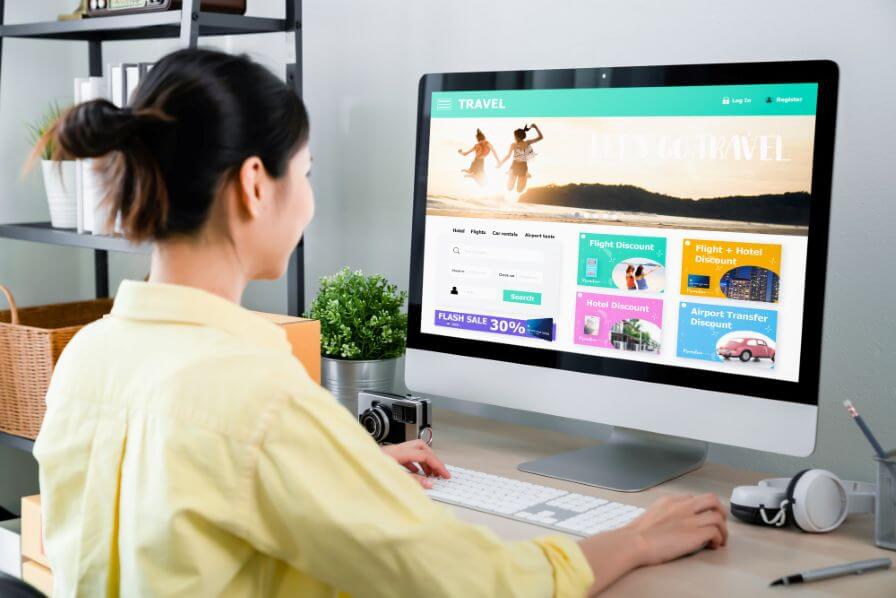
検索上位を狙うには、記事数だけでなく「内容の深さ」も問われます。数だけを追い求めた結果、読者の満足度や滞在時間が下がってしまっては本末転倒です。
- Googleは記事数ではなく「ユーザーの検索意図」を重視
- 重複コンテンツ・量産型SEOのリスクとは?
ここでは、SEOにおいて記事の“量”より重視すべき観点について解説します。
Googleは記事数ではなく「ユーザーの検索意図」を重視
Googleは単なる記事数ではなく、ユーザーの検索意図に応えられる「質の高いコンテンツ」を重視します。
Google公式のSEOスターターガイドでも「ユーザーが何を知りたいか理解し、それに応えるコンテンツを提供すること」が基本とされているのが特徴です。
参照:検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド丨Google
さらには、SEOアルゴリズムはページ数だけで順位を決定せず、コンテンツの「経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)」といった指標を複合的に評価します。
実際に、GoogleのJohn Mueller氏も「ページ数が多いだけでは順位は上がらない」と明言しており、「量より質」の重要性が業界でも共有されています。
参照: Anyone suspect that a site’s total page count affects SEO?
たとえば、あるオウンドメディアで「ただ記事を量産して100本書いた結果、ほとんどが読まれず成果につながらなかった」ケースは十分に考えられます。
一方、検索意図に沿って深く構成した10本の記事では、記事数は少なくてもPVやコンバージョン数が圧倒的に向上する可能性があります。これは「量より質」の影響力を示す典型例です。
このように、記事を量産するのではなく、読者の疑問の核心に答える記事を増やすことが、SEO成功の鉄則です。
【関連記事】【2025年3月版】Googleのアルゴリズムとアップデートの傾向!SEO対策に必要なコツも紹介
【関連記事】【事例有】流入を増やすオウンドメディア記事の書き方と運用のコツ
重複コンテンツ・量産型SEOのリスクとは?
重複コンテンツや量産型SEOは、SEO評価の分散やクローラビリティ低下、ユーザー体験の悪化といったSEO上の重大なリスクを抱えます。成果につなげるためには、量よりも質を重視したコンテンツ設計が欠かせません。
検索エンジンは、同一または非常に類似したコンテンツを多数発見した場合、どれを検索結果に表示すべきか判断に迷い、結果として評価が分散される傾向があります。
また、AIやテンプレート型の文脈で記事を量産すると、表現や構成に類似点が多くなり、記事同士でカニバリゼーション(内容の競合)が発生しかねません。すると、順位も滞在時間も落ちる可能性があります。
したがって、記事を増やす際は、ユーザーにとっての価値や他にはない構成への注力が重要です。
オウンドメディアの記事数がSEOとCVに与える効果とは?
記事数を戦略的に増やすことで、SEOによる流入増加と関連性の高いCV(コンバージョン数)向上の両方を実現しやすくなります。
オウンドメディアの記事数が一定量を超えると、ドメイン全体の評価が高まり、サイトの検索上位表示のチャンスが増える効果があります。
SEOでしっかりとした流入が確保できれば、CRO(コンバージョン最適化)の機会も増加するのがメリットです。さらに、重要ページへの導線を整理した構造的なSEOと、使いやすい導線を設計するUX改善を組み合わせれば、CV数の底上げも可能になります。
弊社Appmartの事例では、BtoBのオウンドメディアで記事制作代行を含むSEOコンサルティングを行った結果、施策開始当初から比べるとオーガニックの流入数が10倍に伸びました。
この事例では、CVの割合も広告と5:5にまで成長しています。CRO施策でも、ページ単位でCVRが1%⇒5%に伸びる結果となりました。

重要なのは、記事の質を維持しつつ数を増やし、SEO流入を確実なCVにつなげる設計です。これにより、オウンドメディアは単なる情報の集積ではなく、持続的な成果を創出する資産型メディアとして機能します。
【関連記事】【2025年最新版】SEO対策の完全ロードマップ!基本から実践的な分析まで徹底解説!
競合サイトは何本書いている?記事数の調査方法
競合サイトの記事数を把握するには、サイトマップから記事数をチェックする方法と、SEOツールを使ってインデックス数やページ構成を細かく分析する手法があります。それぞれの方法を解説します。
サイトマップから記事数を確認する方法
サイトマップ(sitemap.xml)を使えば、記事(URL)数を簡単に把握できます。
記事数の確認方法は、ブラウザで記事数を調べたいサイトのトップページのURLの最後に「/sitemap.xml」をつけてアクセスしてください。
ただ、中にはサイトマップを公開していないサイトもあります。その場合、次項のSEOツールを使う方法を試してみてください。
SEOツールで記事数を確認する方法
SEOツールにより、競合サイトの記事数を効率的かつ正確に確認できます。
SEOツールには専用のクローラー機能が備わっており、サイト構造を網羅的にスキャンしながら、インデックス数やクロール可能ページ、内部リンク構造などを分析することが可能です。記事数以外に、さまざまな角度から競合サイトを分析したい場合はとくにおすすめです。
競合サイトの記事数を把握できる代表的なSEOツールには、Keywordmap、SimilarWeb、Ahrefsが挙げられます。
無料お試し可能なツールもあるので確認してみてください。
参照: Keywordmap
参照: SimilarWeb
参照: Ahrefs
オウンドメディアの記事数を増やす際に注意すべき3つのポイント

「記事を増やせば検索流入が伸びる」と考えている方は要注意です。記事数を増やす過程には、SEO評価を落とす落とし穴も存在します。
- オウンドメディアの更新が目的化しないためのKPIを設計する
- 記事品質の低下を防ぐための編集体制とチェック基準を設ける
- 重複コンテンツは作成しない
ここでは、コンテンツの質を保ちながら記事数を増やす際に、見落としてはならない3つの視点を紹介します。
オウンドメディアの更新が目的化しないためのKPIを設計する
オウンドメディアでは、記事数など「更新そのもの」を目的とするKPIを避け、最終的なKGI(例:リード獲得数やCV)に直結する、成果志向のKPIの設定が重要です。
更新そのものを目標にしてしまうと、“量”だけを追う運用になりやすく、質や最終的な成果が置き去りになりかねません。
たとえば、リード獲得を目的とするなら、「月間CV数」や「CVR」をKPIに設定します。さらに、その手前のプロセスとして「セッション数」「検索流入数」「回遊率」など複数のKPIをKPIツリーで整理するのがおすすめです。
このように、更新頻度や記事数だけに依存しない運用設計を行うと、成果への因果関係が見えやすくなります。
オウンドメディアのKPIツリーについては、以下記事で詳しく解説しています。
【関連記事】オウンドメディアの平均PV数は?目安・改善策・KPI設定まで解説
記事品質の低下を防ぐための編集体制とチェック基準を設ける
記事数を増やす場合、編集体制と明確なチェック基準があれば、記事の品質を落とさずに安定して記事数を増やせます。
オウンドメディアの記事の品質・一貫性を保つための役割分担ができている編集体制がないと、誤字脱字や構成の甘さ、SEO対策不足が積み重なり、ユーザー評価や検索順位が下がりかねません。
たとえば、弊社Appmartでは、コンテンツの「Wチェック体制」(ツール+人による校正)を採用することで、記事内容の正確性と文章の品質を担保しています。Webディレクターによるディレクションを通じて、記事の構成作成から校正・校閲まで徹底して行う体制が整っている点が特徴です。
記事の質を犠牲にせず記事数を増やすには、このような編集体制とチェック基準の整備が必要になります。
重複コンテンツは作成しない
オウンドメディアでは、記事数を増やす際に「重複コンテンツ」を作成しないようにしましょう。
同じテーマやキーワードを扱った類似記事がサイト内に複数あると、Googleはコンテンツの重複とみなし、評価を分散させたり、最悪の場合はインデックス除外となったりする場合もあります。
例として、「SEO対策 初心者向け」というテーマの記事を複数公開すると、検索順位が競合し合い、どの記事も上位に表示されなくなりかねません。
そのため、「SEO対策 初心者向け 記事 書き方」「SEO対策 初心者向け ブログ 集客」といったロングテールキーワードを活用して内容の切り口に差をつけ、1記事ごとの独自性を確保しましょう。
オウンドメディアの記事数を効率的に増やす方法と体制作りのコツ
記事数がSEO成果の土台になるとはいえ、ただやみくもに増やしても効果は薄いのが現実です。
- 記事作成を内製する場合のリソース計画
- 外注・記事制作代行会社の活用メリット
ここでは、戦略的に記事数を伸ばすための方法と、外注・内製を組み合わせた体制作りについて解説します。
記事作成を内製する場合のリソース計画
オウンドメディアの記事を内製で増やす際は、担当者の役割の明確化と必要な工数・スキルを想定したリソース計画が成果に直結します。
記事制作の内製化では、社内ノウハウやブランドの統一性を保てます。一方で、人的リソースが不足すると、コンテンツ制作の質や更新の継続性が損なわれかねません。
内製化の成功例として、SEOや編集のスキルを持つ専任担当者を配置し、月間更新記事数を確保しながら、内部にノウハウを蓄積していく方法が挙げられます。
記事制作の内製化を活かすには、量だけでなく「誰が、何記事、どの程度の質で書くのか」を設計する体制構築が持続的な成果につながります。
外注・記事制作代行会社の活用メリット
外注やSEO記事制作代行を活用すれば、専門性の高い記事を短期間に、一貫した品質で効率的に量産できます。
記事制作代行サービスでは、専門のライターやマーケターが記事を制作します。そのため、SEO対策や記事構成の質が担保される上に、自社担当の負担や制作遅延リスクを回避できるのがメリットです。
弊社Appmartの記事制作代行では、オウンドメディアのセッション数が「3.5倍以上」増加した成功事例があります。詳細は以下記事にてご覧いただけます。
【関連記事】運営開始後からセッション数368%UP。相談のしやすさが成果に直結
成果に直結する記事数を「量」ではなく「質」と「速度」で補うには、外注の戦略的活用が、効果の高い選択肢となり得ます。
オウンドメディアに必要な記事数は「戦略」と「目的」で決まる
SEOで成果を出すために必要なオウンドメディアの記事数は30〜50記事がひとつの目安とされています。しかし、重要なのは単なる量ではなく「記事の質と構成の戦略性」です。読者が知りたいことを漏れなく・わかりやすく・順序立てて網羅するように記事全体の流れや見出しを設計すれば、Googleからの評価を積み上げられます。
とくに、「記事を読んだ後の行動(CTA到達率)」や「回遊率」のような中間KPIを見据えた設計が不可欠です。狙うキーワードの難易度とWebサイトのドメインパワーに応じて、作成する記事内容の優先順位も明確にしましょう。
弊社Appmartのオウンドメディア制作では、オウンドメディアの戦略立案からキーワード選定、競合分析、記事執筆、投稿・改善まで一括して支援を行っています。
成果につながる導線を設計した“売上に直結する”オウンドメディアを構築したい場合は、ぜひ一度、下記リンク先よりオウンドメディア制作の詳細をご覧ください。