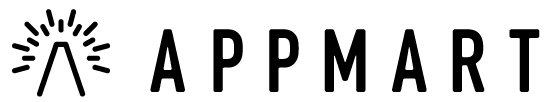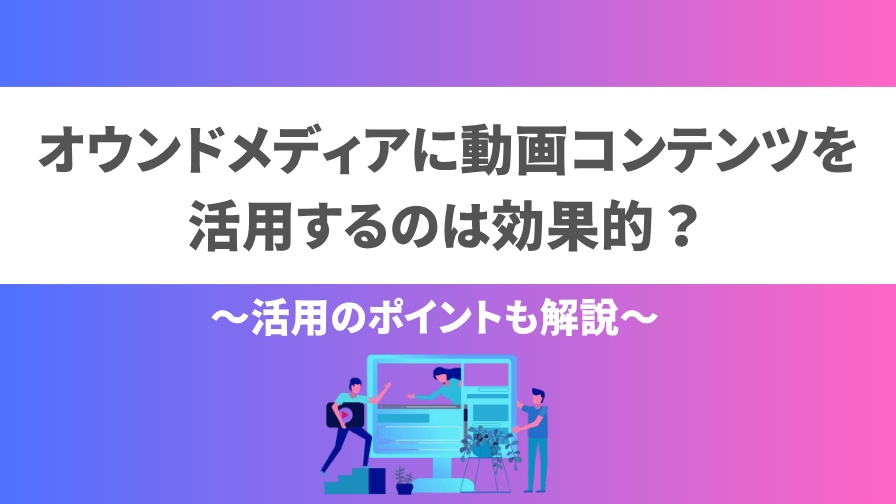・さまざまなチャネルとの親和性が高い動画コンテンツはオウンドメディアにおいても需要が増加している
・オウンドメディアにおける動画コンテンツは、多様な目的に活用できる
・目的に応じて動画の種類を使い分けていくことが重要
ユーザーの情報収集行動が変化していくなかで、オウンドメディアに動画コンテンツを効果的に取り入れることは、差別化において、また、UXの観点でも重要といえます。本記事では、オウンドメディアにおける動画活用のメリットや注意点、具体例、効果的な使い方を解説します。
もくじ
オウンドメディアにおいて動画コンテンツの需要が増加している背景

オウンドメディアにおいて動画コンテンツの需要が増加している背景は以下のポイントに起因しています。
・ユーザーの情報収集行動の変化
・SNSやYouTubeなど外部チャネルとの親和性
・SEO上の評価
上記について本項で解説していきます。
ユーザーの情報収集行動の変化
現代のユーザーは、短時間で多くの情報を得られる手段を好む傾向があります。特にスマートフォンの普及により、テキストを読むよりも読むことで情報を収集する傾向は強まっているといえるでしょう。
動画は視覚と聴覚の両方で内容を伝えられるため、情報伝達の効率においてテキストベースのコンテンツにも劣りません。こうした背景から、オウンドメディアにおける動画コンテンツの重要性が年々高まっています。
SNSやYouTubeなど外部チャネルとの親和性
動画コンテンツは、SNSやYouTubeといった外部チャネルとの相性も抜群です。SNS上でシェアされやすく、拡散性にも優れているため、オウンドメディアへの新規流入を促す導線としても機能します。
また、YouTubeにアップした動画をオウンドメディアに埋め込むことで、外部流入と自社サイト内の回遊率向上を同時に狙うことが可能です。
SEO上の評価
Googleは近年、ユーザー体験を重視した検索アルゴリズムへと進化しており、ページ内に動画があることで、滞在時間の向上や直帰率の改善につながります。
そのため、動画コンテンツの配置は間接的に検索順位の改善が期待できます。加えて、YouTube動画が検索結果の上位に表示されるケースも増えており、動画とSEOの連携は重要性を増しています。
オウンドメディアに動画を取り入れるメリットとは?

続いて動画コンテンツをオウンドメディアに取り入れるメリットについて、本記事では以下の点から解説していきます。
・コンバージョン率向上につながる
・情報量の強化につながる
・多彩な目的で活用できる
・他チャネルとの連携による集客拡大が期待できる
コンバージョン率向上につながる
動画は、テキストや画像よりも多くの情報を短時間で伝えられるため、商品やサービスの魅力をダイレクトに伝えることができます。
自社商材やサービスに対するユーザーの理解が深まることで、不安や疑問を解消しやすくなり、コンバージョンにつながる可能性も高まるでしょう。また、フォーム誘導や資料請求などの前に動画を配置することで、行動喚起の効果も期待できるため、CVR改善につながります。
情報量の強化につながる
複雑な内容や言葉で説明しづらい情報も、動画であれば視覚的にわかりやすく伝えることができます。図解や動きを用いて直感的に説明できる点は、テキストコンテンツにはない動画のメリットです。
たとえば、製品の使い方や操作方法などは、文章よりも動画で示したほうが理解しやすいため、ユーザー満足度向上にもつながります。
多様な目的で活用できる
動画は、商品紹介やFAQ、インタビュー、採用活動など、多用途に活用できます。コンテンツの目的やターゲットに合わせて動画の内容を変えることで、企業のメッセージを最適な形で伝えることが可能です。
また、一度制作した動画は複数のチャネルに再利用できるため、コンテンツ資産としての価値も高い点も強みといえるでしょう。
他チャネルとの連携による集客拡大が期待できる
動画コンテンツは、SNS広告やYouTube、メールマーケティングなどの他チャネルと連携させることで、高い集客効果を発揮します。
たとえばYouTubeで公開した動画からオウンドメディアへのリンクを貼ることで、新たなユーザー層を呼び込むことができます。動画とテキストメディアの役割を明確にし、相互補完的に運用することで、集客チャネルを多角化できるのが大きな魅力です。
オウンドメディアで動画を活用する際の注意点

続いて、オウンドメディアで動画を活用する際の注意点を以下のポイントから解説していきます。
・制作コスト・リソースを確保する
・ユーザー体験に悪影響を及ぼさないよう注意する
・記事コンテンツとの親和性に注意する
制作コスト・リソースを確保する
動画制作には、企画・撮影・編集などの工程が発生するため、一定のコストと工数が必要です。特にクオリティの高いコンテンツを目指す場合、社内リソースだけでは対応が難しいケースもあります。
あらかじめ予算や体制を見直し、外注も含め、実現可能な範囲で計画を立てることが大切です。また、多くのリソースを割くだけの価値があるかどうか、目的とのバランスを見極めましょう。
ユーザー体験に悪影響を及ぼさないよう注意する
動画を埋め込むことでページの表示速度が遅くなる、音声の自動再生がユーザーのストレスにつながるといった場合があります。UXに悪影響を与えてしまうと、結果的に離脱率や直帰率の悪化を招く恐れがあるでしょう。
UXへの悪影響を避けるためにも、動画の設置方法やファイルの軽量化、音声のオンオフ設定などを適切に管理し、ユーザーにとって快適な閲覧体験を提供することが求められます。
記事コンテンツとの親和性に注意する
動画はあくまで補完的な役割であり、記事コンテンツとの整合性が取れていなければ逆効果になる可能性もあります。記事のテーマと無関係な動画を挿入すると、ユーザーの混乱を招くだけでなく、サイト全体の信頼性にも影響を与えることがあります。
たとえば、採用オウンドメディア上で自社商材の紹介動画を設置しても、ユーザーにとって有益な情報とはなりにくいでしょう。このように、まずは動画の設置位置や内容が記事の目的に沿っているかを確認し、文脈に合った活用を心がけましょう。
オウンドメディアで活用できる動画コンテンツの具体例とは?
本項では、オウンドメディア上で活用できる動画コンテンツの具体例を、実際の事例を交えて紹介していきます。
・商品・サービス紹介動画
・導入事例・インタビュー動画
・HowTo・FAQ動画
・採用活動向け動画
・イベント・セミナー動画
商品・サービス紹介動画
建材メーカー・オカムラが提供するロボットストレージシステム「虎の穴」紹介動画では、通信販売・メーカー業界の知見を活かし、倉庫での実作業風景やシステムの自動動作を映像化したコンテンツを公開しています。
製品スペックだけでなく、実際の作業効率向上の様子を動画形式で可視化することで、購買検討へ導く構成になっている点が特徴的です。
参照:オカムラ納入事例
導入事例・インタビュー動画
クラウド勤怠管理システム「SmartHR」を導入した製造業・遠山産業によるインタビュー動画です。
動画内では、給与計算や勤怠管理が一元化されたことにより、ミス削減や業務負担の軽減が実感される様子を従業員の生の声で伝達しています。製造業という業種のリアルな課題解決ストーリーとして説得力があるコンテンツといえるでしょう。
参照:SmartHR
HowTo・FAQ動画
JETRO(日本貿易振興機構)が公式に公開している「How to Set up Business in Japan」というFAQ・HowTo動画です。
初回の「Types of Operation in Japan」では、日本で会社設立時に選べる3つの法人形態(株式会社、支店、代表事務所)について、各形式の違いやメリット・デメリットを動画で解説しています。全体的に初学者でも理解しやすい構成となっている点が特徴です。
このようなFAQ動画は、複雑な制度や選択肢を抱えるオウンドメディアにおいて、ユーザーの疑問解消と信頼感構築に有効です。
参照:JETRO
採用活動向け動画
刃物・キッチン用品メーカー「貝印」が公式YouTubeで公開している新卒採用動画「KAI GROUP CUTTING EDGE SPIRIT」の例です。
動画は、企画・デザイン・製造まで多様な職種の社員が登場し、自らの仕事観やモチベーションを語るという内容になっています。職場のリアルな熱量や社風を伝えることで、求職者が入社後のイメージをしやすい採用活動向け動画といえるでしょう。
参照:貝印
なお、自社の採用活動にオウンドメディアを活用する場合、以下の記事で採用オウンドメディアについて解説しています。あわせてチェックしてみてください。
【関連記事】【2025年版】採用オウンドメディアとは?成功事例・メリット・運用方法まで徹底解説
イベント・セミナー動画
伊藤忠テクノソリューションズは、CシアターというビジネスITの課題解決につながる動画コンテンツを活用しています。同社が定期開催しているBtoB向けウェビナーのアーカイブをオウンドメディア上で配信する形式です。
動画コンテンツにより、イベント参加者以外にも情報を届け、リード獲得やナーチャリングへの導線構築に成功しています。
動画コンテンツをオウンドメディアで効果的に活用するポイント
続いて本項では、動画コンテンツをオウンドメディア上で効果的に活用するポイントを、以下の点から解説していきます。
・目的に応じて動画を使い分ける
・テキストコンテンツと組み合わせる
・動画の見せ方を工夫する
・再生状況やCVRを分析してPDCAを回す
目的に応じて動画を使い分ける
動画をただ掲載するだけでは、効果は限定的です。認知拡大・信頼獲得・CV促進など、目的ごとにコンテンツの形式や内容を最適化することが重要です。
たとえば、採用目的であれば職場の雰囲気が伝わるドキュメンタリー形式、商品説明ならアニメーションやナレーション付きの解説動画が効果的です。まずは目的を明確にした上で、視聴者に「何をしてほしいのか」を意識した構成を設計することで、動画の成果向上が期待できるでしょう。
なお、オウンドメディアにおける基本的な役割については以下の記事で詳しく解説しています。興味のある方はあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】オウンドメディアの役割とは?成果を出す運用のポイントも解説
テキストコンテンツと組み合わせる
動画単体ではSEO効果が限定的なため、テキストと組み合わせることが重要です。たとえば、動画の内容を文字起こしし記事内に掲載すれば、検索エンジンにも内容が伝わりやすくなります。
また、動画を補足するQ&Aやポイント要約をテキストで示すことで、視聴しない読者にも内容を届けることが可能です。さらに、読みながら視聴を選べる構成にすることで、ユーザーの情報取得スタイルにも柔軟に対応できます。
動画の見せ方を工夫する
動画の設置位置や再生方法も、視聴率に大きく関わる要素です。たとえば、記事冒頭やCTA直前など、注目が集まりやすい位置に配置することで、再生される確率が高まります。
また、自動再生やミュート再生など閲覧環境に配慮した設定も重要です。デザインや配置によって動画が効果を発揮するかどうかが左右されるため、見せ方には細心の注意が必要です。
再生状況やCVRを分析してPDCAを回す
動画も他のWeb施策と同様に、効果検証と改善のサイクルが欠かせません。YouTubeをはじめとしたプラットフォームでは、再生回数や視聴維持率、離脱ポイントなどを可視化できます。
データを活用すれば、どの部分で関心を失っているか、どのCTAで成果が出ているかを分析可能です。結果をもとにサムネイルや導入部分の構成を見直し、継続的に改善していくことで、動画の成果を最大化できます。
動画を活かしてオウンドメディアの効果を高めよう
動画は、情報伝達力と視覚的にメッセージを伝える力に優れており、商品理解の促進や信頼性の向上、コンバージョン率の改善に貢献します。紹介動画やインタビュー、HowTo、採用、イベントなど、目的に応じた形式を使い分けることで、オウンドメディアの価値を最大限に引き出せます。ターゲットに合わせた構成と、活用後の分析も意識し、効果的に運用しましょう。