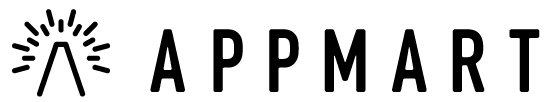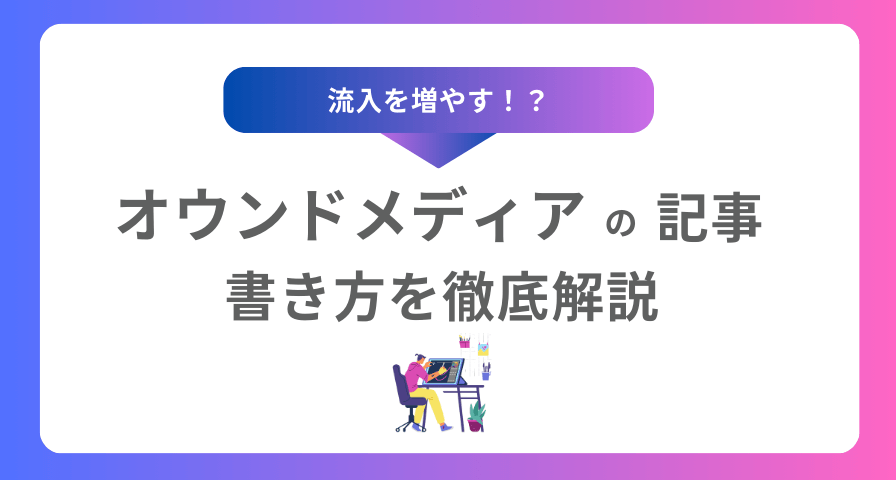
オウンドメディアは、ブランドの認知度を高め、リードを獲得し、長期的な顧客関係を築くための重要なツールです。しかし、記事の書き方がわからず困っているという場合もあるでしょう。
この記事では、オウンドメディアの流入を増やす効果的な記事の書き方や運用のポイントを紹介しています。具体的な事例を交えながら解説するため、すぐに実践可能なノウハウを得られるはずです。
もくじ
オウンドメディアの持つ本質的な価値とは?
オウンドメディアが持つ本質的な価値は以下の通りです。
- 信頼性向上:企業やブランドが自らの声を直接ユーザーに届けることができる
- 自社の情報を正確かつタイムリーに発信できる
- SEO対策を講じることで見込み顧客の流入が見込める
- 流入増に伴いリード獲得にもつながる
- 見込み顧客と長期的な関係を築ける
- ブランド認知度を向上させられる
上記の価値を享受するには。流入を増やすため記事の書き方をマスターする必要があります。次の章から早速解説します。
【関連記事】【事例つき】オウンドメディアの意味や目的をわかりやすく解説
記事作成の基本ステップ
流入を増やすためのオウンドメディア記事作成には、いくつかの基本的なステップがあります。ここでは、成功に導くための基本的な手順を順を追って説明します。これにより、効率的に質の高いコンテンツを生み出すことができるはずです。
ステップ1. 目的とゴールの設定
まず最初に考えるべきことは、記事作成の目的とゴールの設定です。なぜ記事を書くのか、その記事で達成したい具体的な成果は何なのかを明確にしましょう。これにより、記事の方向性がぶれず、読者に対して一貫したメッセージを伝えることができます。
ステップ2. ターゲットユーザーとペルソナの設定
次に行うべきは、ターゲットユーザーとペルソナの設定です。ターゲットユーザーとは、この記事を読むことを想定している人々のことです。ペルソナはそのターゲットユーザーを具体的にイメージした架空の人物像です。これを明確にすることで、読者にとってより役立つ情報を提供することができます。
ステップ3. キーワード選定とリサーチ
目的とゴール、ターゲットユーザーが明確になったら、次に行うべきはキーワード選定とリサーチです。
キーワード選定は、ユーザーが検索エンジンで使用する言葉を特定する作業を指します。適切なキーワードを選ぶことで、SEO効果を高めることが可能です。集客用のキーワードとコンバージョンを狙う用のキーワードを区別できるとより理想的です。
また、リサーチを通じて関連情報を集めることで、記事の信頼性と質を向上させることも忘れないようにしましょう。検索では見つけられないような一次情報を掲載することも上位化のためには必要です。
サジェストワードや関連キーワードの活用
キーワード選定の際には、サジェストワードや関連キーワードも調べておきましょう。サジェストワードとは、検索エンジンが自動的に提案する関連検索語句のことです。これを参考にすることで、ユーザーが実際にどのようなキーワードで検索しているかを把握できます。
また、関連キーワードを使用することで、多くのユーザーにリーチしやすくなります。
例えば、検索エンジンで「オウンドメディア 記事」と入力すると、その後に続くキーワードや関連する他のキーワードが提案されることがあります。これを参考にすることで、より具体的でユーザーの需要に合ったコンテンツを作成することが可能です。
なお、関連キーワードは無料で調べることができます。無料ツールでおすすめなのはラッコキーワード です。参考にしてみてください。
検索ボリュームの確認
キーワードを決定したら、その検索ボリュームを確認することが重要です。
検索ボリュームとは、ある特定のキーワードがどれだけ頻繁に検索されているかを示す指標です。高い検索ボリュームのキーワードを選ぶことで、多くのユーザーに記事を読んでもらうチャンスが増えます。
例えば、GoogleキーワードプランナーやUbersuggestなどのツールを使用すれば、検索ボリュームや関連キーワードのデータを簡単に入手できます。ボリュームが高いほど上位化させる難易度は高くなり、ボリュームが少ないほど上位化させやすい傾向にあります。
サイト立ち上げ当初はボリュームが少ないキーワードから制作をし、徐々に上位化させていくのがセオリーです。
競合サイトの調査
競合サイトの調査も欠かせません。他のサイトがどのような内容で記事を書いているのかを分析することで、自分の記事に取り入れられる良い手法や、逆に避けるべき点を見極めることができます。また、競合サイトがどのようなキーワードを使っているかを確認することも重要です。
競合サイトの調査には、検索エンジンで実際にターゲットキーワードを検索する方法や、AhrefsやSEMrushなどのツールを使用する方法があります。
これにより、記事の質を高め、差別化を図るための有用な情報を得ることができます。競合を分析し、その上で独自の価値を提供する記事を作成することが、成功の鍵となります。
ステップ4. ユーザーの検索意図に合致した構成の作成
ユーザーの検索意図に合致した記事構成を作成することで、読者に求められる情報を的確に提供できます。具体的な手法は以下の通りです。
検索上位10記事の内容を確認する
検索上位に表示される10記事の内容を確認することは、記事作成の初期段階で非常に重要です。トップ10記事は、既に多くのユーザーに評価されているコンテンツであり、検索エンジンがその有用性を認めているものです。これらの記事を分析することで、何が求められているのかを理解できます。
まず、内容の深さと質を評価しましょう。どのようなテーマが詳しく説明されているか、どのような視点から情報が提供されているかを確認します。これにより、あなたが書こうとしている記事に対する読者の期待値を把握できます。
次に、使用されているキーワードやフレーズをメモします。これらのキーワードは、SEO対策にも役立ちます。特に、見出しやサブ見出しにどのようなキーワードが使われているかを確認することが重要です。
また、ビジュアル要素も評価対象です。画像、動画、インフォグラフィックなどがどの程度使われているかを確認し、それらがどのようにコンテンツに組み込まれているかを分析しましょう。
最後に、ユーザーエンゲージメントの指標として、コメント数やシェア数、ソーシャルメディアでの言及なども参考にします。これらの要素は、コンテンツの反響を測る指標となるため、記事作成時に役立つ情報です。
ターゲットを理想の状態に導くためのストーリー展開を考える
ターゲットユーザーが理想の状態に到達するためのストーリー展開を考えることは、読者を引き込むために不可欠です。ストーリーは、ユーザーの問題や悩みを解決する道筋を提示するものであり、読者に行動を促す際に非常に効果的です。
まず、ターゲットユーザーのペルソナを明確にしましょう。ペルソナ設定により、ユーザーのニーズや関心を具体的に理解できます。たとえば、マーケティング担当者をターゲットとする場合、広告費の最適化やリードの質の向上といった具体的な課題を意識します。
次に、そのペルソナが抱える具体的な問題を提示します。そして、その問題をどのように解決するか、そのプロセスをストーリーの流れとして構築します。このプロセスには、現状の分析、課題の解決方法、期待する成果など、ステップバイステップで説明します。
さらには、成功事例や具体的なデータを挿入することで、信憑性を高めます。実例を交えることにより、読者は記事が現実的で実行可能なアドバイスを受けられていると感じ、内容ひいてはそのメディアに信頼感を抱きます。
最後に、結論部分で読者に行動を促すアクションプランを提示します。例えば、ダウンロード可能なテンプレートやリソースの提供、現状の見直しのためのチェックリストの提示などです。これにより、読者が実際に行動を起こしやすくなり、記事の有用性が一層高まります。
Q&Aサイトもチェックできるとなおよし
Q&Aサイトを活用することは、ユーザーの具体的な疑問や関心を把握するための有力な手段です。オウンドメディアの記事作成において、読者のニーズに直結する内容を提供できます。
まず、Q&Aサイトで関連するキーワードを検索します。例えば、オウンドメディアについての記事を作成する場合、「オウンドメディア 記事 作成」や「SEO対策 オウンドメディア」といったキーワードを使用します。これにより、ユーザーが実際にどのような質問をしているかを確認できます。
次に、その質問内容を整理し、頻出するテーマや共通する疑問を抽出します。これらの情報を基に、記事内容に反映させることで、読者が求める情報を的確に提供できます。例えば、多くの質問が「どのようにSEO対策をすれば良いか」に集中している場合、その具体的な手順や成功事例を記事に盛り込むことが有効です。
さらに、回答部分もチェックします。他のユーザーがどのような回答をしているかを分析し、それが有効かどうかを評価します。これにより、記事に反映する際に、より精度の高い情報を提供できます。
また、Q&Aサイトに投稿された質問の多くは、自ら情報を探す時間がないユーザーや、専門知識が不足しているユーザーによるものです。このため、記事内容はできるだけ具体的かつ簡潔にまとめ、初心者でも理解しやすい表現を心掛けることが重要です。
このようにしてQ&Aサイトを活用することで、読者のニーズにより一層マッチしたオウンドメディアの記事を作成することができます。結果として、SEO効果の向上やユーザーエンゲージメントの強化に寄与するでしょう。
ステップ5. 魅力的な見出しとタイトルの作成
魅力的な見出しとタイトルは、読者の関心を引きつけるために非常に重要です。ステップ5では、オウンドメディア記事において効果的な見出しとタイトルの作成方法を具体的に説明します。
まず、見出しの作成では、ターゲットユーザーが検索エンジンで使用するキーワードを活用することが重要です。これは、検索エンジンでの上位表示を目指すSEO対策の一環です。例えば、「効果的なオウンドメディアの活用方法」といった具体的なキーワードを含めるとよいでしょう。
さらに、読者の興味を惹くために、疑問形や数字を取り入れることも有効です。例えば、「オウンドメディアで成功するための5つの秘訣」や「なぜオウンドメディアが今注目されているのか?」など、読者が続きを読みたくなるような見出しにすることがポイントです。
加えて、タイトルは簡潔でありながらも内容を的確に伝えることが大切です。タイトルが長すぎたり抽象的すぎると、読者の興味を失ってしまう可能性があります。ターゲットユーザーが具体的な情報を求めていることを意識し、明確な表現を選びましょう。
最後に、見出しとタイトルは一度作成して終わりではなく、定期的に見直すことも大切です。検索トレンドや読者の反応を基に改善を繰り返すことで、より効果的な見出しとタイトルを作成する能力が向上します。
ステップ6. 記事の執筆と見直し
記事の執筆は、情報整理と構成作業を終えた後に行います。まず、導入部分で読者の目を引く魅力的な書き出しを心掛けます。この際、ターゲットユーザーが求めている情報や解決策を簡潔に提示すると効果的です。また、記事全体のトーンとスタイルを統一し、一貫性を持たせることは非常に重要です。
次に、記事の本論部分では、見出しごとに明確なテーマを設定し、順序立てて説明します。具体的な事例やデータを交えることで、情報の信憑性と説得力を高めることができます。そして、内容が重複しないよう、前後の段落や他の見出しとの関連性に留意してください。
記事の執筆が完了したら、必ず見直しを行います。まず誤字脱字の修正を行い、次に文法や表現の不自然さをチェックします。第三者に見てもらうことで、新たな気づきを得ることもあります。このプロセスを丁寧に行うことで、読みやすく品質の高い記事を提供できるようになります。
ステップ7. 記事執筆はWebライティングを意識する
Webライティングでは、キーとなるキーワードを的確に使用し、ターゲットユーザーが求める情報をコンパクトに伝えることが求められます。読みやすさを意識し、段落や箇条書きを駆使すると良いでしょう。
特にPREP法を意識したライティングが重要です。結論-理由-例-結論の順で文章を記載することで、わかりやすくWebで読みやすい文章ができあがります。
わかりやすく読みやすい文章が書ければ、その記事でのユーザーの滞在時間が伸びやすくなり、SEO評価向上が見込めます。
写真や動画で記事を補完することも重要
記事の内容をより豊かにし、ユーザーの関心を引き続けるためには、写真や動画といった視覚的なコンテンツを活用することも重要です。例えば、製品紹介の記事の場合、実際に使用しているシーンの画像や動画を挿入することで、読者が具体的なイメージを掴みやすくなります。
また、インタビュー記事やケーススタディでは、登場人物や現場の写真を使用することで、ストーリーに臨場感が加わります。
写真や動画を使用する際は、高解像度のものを選び、記事の主題に直結する内容を選ぶことが大切です。過剰な視覚効果は読者の集中を妨げる場合があるため、適度なバランスが求められます。さらに、画像のキャプションや動画のサブタイトルを細かく設定することで、SEO対策にも効果的です。
記事公開後のフィードバックと効果測定も重要
記事公開後のフィードバックと効果測定は、オウンドメディアを成功させる上で欠かせません。ユーザーの反応を見て、どの記事がどのような影響をもたらしているのかを確認することで、今後の戦略を精緻化する手助けとなります。
記事の効果測定方法
記事の効果測定方法には、いくつかの重要な指標があります。まず、Google Analyticsを活用して、訪問者数や閲覧ページ数、平均滞在時間などのデータを収集します。これにより、どの記事がユーザーに最も読まれているかを分析できます。
次に、コンバージョン率をチェックします。記事をきっかけに商品の購入や問い合わせがどれだけ発生したかを確認し、記事の実際の効果を見極めます。さらに、SNSでの反響も重要です。シェアやコメントの数、読者からのフィードバックを収集することで、記事がどの程度ユーザーに響いたかを把握します。
最後に、SEOの観点からも効果を測定します。Google Search Consoleを活用して記事が検索エンジン結果ページでどの位置に表示されているか、どれだけのオーガニックトラフィックを生み出しているかをチェックします。これらの指標を総合的に分析することで、記事の成功度を評価し、次の記事作成に反映させることができます。
【関連記事】SEO分析が重要な理由とチェックしておきたい項目
改善とメンテナンス
記事の改善とメンテナンスは、オウンドメディア運営の持続的な成功にとって欠かせません。まず、定期的に既存の記事を見直し、内容が古くなっていないか、新しい情報を追加する必要があるかを確認します。
また、検索エンジンのアルゴリズム変更に対しても対応が必要です。SEOの最新トレンドを取り入れ、キーワードの見直しや内部リンクの最適化を行いましょう。さらに、アクセスデータを元に低パフォーマンスの記事を特定し、改善の余地がある部分を洗い出します。これにより、全体的なコンテンツ品質を向上させ、ユーザーエンゲージメントを高めることができます。
【関連記事】【2025年3月版】Googleのアルゴリズムとアップデートの傾向!SEO対策に必要なコツも紹介
オウンドメディア記事の内製/外注のメリット・デメリット
オウンドメディアの記事作成において、内製するか外注するかは非常に重要な選択です。それぞれのアプローチには固有のメリットとデメリットが存在します。
内製のメリット・デメリット
オウンドメディアの記事を内製することにはいくつかのメリットとデメリットがあります。メリットとしては、まず、社内で直接コミュニケーションを取ることができるため、コンテンツが企業のビジョンや目標に沿ったものになりやすい点です。
また、内部の専門知識や会社独自の情報をリアルタイムに活用できるため、他社にはない独自性のあるコンテンツを作成することができます。さらに、長期的にはコストを抑えることも可能です。
しかし、内製にはデメリットも存在します。まず、記事作成には時間と労力がかかるため、他の業務に割ける時間が減少する可能性があります。また、コンテンツ作りに慣れていない社員が関わる場合、品質が安定しないこともあるでしょう。
加えて、SEO対策や最新のマーケティング手法に関する知識が社内に欠けている場合、せっかくの記事が効果を発揮しない可能性もあります。このため、内製を選択する際は、社内のリソースとスキルを十分に評価することが重要です。
外注のメリット・デメリット
外注でオウンドメディア記事を作成することには多くのメリットがあります。まず、プロのライターやマーケティングスペシャリストを雇うことで、高品質でSEOに最適化されたコンテンツを安定して制作できる点です。
外部の専門家は最新のトレンドや技術に精通しているため、効果的なコンテンツ戦略を立てることができます。また、社内リソースを温存できるため、本業に集中することができます。
しかし、外注にもデメリットが存在します。まず、外部とのコミュニケーションが増えるため、コンテンツが企業のビジョンや目標に完全に一致しない可能性がある点です。また、外注費用がかさむことがあり、予算の問題を引き起こすこともあります。
さらに、社内の独自性や専門知識を完全に反映することが難しい場合もあるでしょう。外注を行う際には、外注先とのコミュニケーションを密に行い、企業の意図を十分に理解してもらうことが成功の鍵となります。
【関連記事】オウンドメディア外注は逆効果!?メリットや費用相場・代行企業の選び方を紹介
オウンドメディアの記事は会社の資産として「価値を生み出す存在」にすべし!
オウンドメディアの記事は単に情報を提供するだけでなく、企業やブランドの価値を直接的に反映する重要な資産です。
なぜなら、質の高い記事は長期的に検索エンジンからの流入を維持し続け、集客力を高め、見込み顧客との接点を増やすためです。さらに、権威性の高いコンテンツは信頼性を築く助けとなり、顧客との強固な関係を構築します。
リード獲得にも効果的で、見込み顧客の興味を引き付け、コンバージョンを促進する役割を果たすでしょう。これにより、広告費用を削減しつつ、持続可能なビジネスモデルを実現することが可能になります。オウンドメディアの記事が戦略的に運用されることで、企業のブランド力と収益向上を同時に達成可能です。
Appmartのオウンドメディア運用代行サービスはこちら
https://appmart.co.jp/owned-media/